

箏とは
箏は、奈良時代に中国から伝わってきた楽器といわれています。
古くは宮中音楽の伴奏楽器として演奏されていましたが、
時代とともに発展していく中で、室町時代には独奏楽器として〝箏曲〟というジャンルが確立しました。
江戸時代には盲目の演奏家により数多くの箏の曲が作曲され、
三絃(三味線)や尺八との合奏も盛んに行われるようになり(=三曲合奏)、
やがて庶民的なお座敷音楽としても親しまれる身近な楽器となりました。
多様な奏法で幅広い表現が可能なことから、現代では洋楽器との合奏や、
ポップスやクラシックなど、様々な形態やジャンルで演奏されています。
百人一首や源氏物語に登場する“貴族のお姫さまが弾く楽器”のような、
敷居の高いイメージがあるかもしれませんが、決してそんなことはなく、
老若男女を問わずどなたでも気軽に楽しむことのできる楽器です。
もっと見る
〝コト〟というと、「琴」が常用漢字なため、
「琴」と表記するんじゃないの?と思われる方もいらっしゃると思いますが、
「箏」の字が使われるようになったのには、歴史に基づいた理由があります。
コトの歴史は古く、静岡の登呂遺跡から発掘されたことから、
少なくとも2千年前から日本にあったとされています。
日本古来のコトは、6本の絃が張ってある〝和琴〟と呼ばれるもので、
ギターやバイオリンのように、左手の指で絃を抑えて音程をつくり、右手の指で直接絃を弾くのが特徴です。
派生楽器である一絃琴、二絃琴も同様です。
対して、奈良時代に中国から伝わったとされ、13本の絃を有し、
柱を立て、右手の指にはめた爪で奏するコトが、〝箏〟です。
琴も箏もどちらも〝コト〟と呼ばれ、やがて、柱がないコトを「琴(きん)のコト」、
柱を立てて奏するコトを「箏(そう)のコト」と、区別するようになりました。
ところが、次第に箏のコトが主流となり、琴のコトが演奏される場面が極端に少なくなったことを理由に、
箏のコトを一般的な〝コト〟と呼ぶようになり、表記も「箏」の字が使われるようになりました。
江戸時代に、八橋検校により現在の形に改良されるとともに、
奏法や楽式も新たに確立され、大きく発展した箏。(京都の銘菓「八ツ橋」の由来となったという説もあります。)
絃の本数が13本の箏を基本とし、時代とともに十七絃、二十絃、二十五絃、三十絃と、
絃の本数の多い箏がつくられました。
遡ると、八橋検校を筆頭に、宮城道雄や沢井忠夫といった箏の先駆者により様々な奏法が取り入れられ、
西洋音楽の影響も受けてきた歴史もあるため、時代に合わせて色々な意味でバリエーションが増えたのは、
必然ともいえるでしょう。
箏とは
箏は、奈良時代に中国から伝わってきた楽器といわれています。
古くは宮中音楽の伴奏楽器として演奏されていましたが、時代とともに発展していく中で、室町時代には独奏楽器として〝箏曲〟というジャンルが確立しました。
江戸時代には盲目の演奏家により数多くの箏の曲が作曲され、三絃や尺八との合奏(=三曲合奏)も盛んに行われるようになり、やがて庶民的なお座敷音楽としても親しまれる身近な楽器となりました。
多様な奏法で幅広い表現が可能なことから、現代では洋楽器との合奏や、ポップスやクラシックなど、様々な形態やジャンルで演奏されています。
百人一首や源氏物語に登場する“貴族のお姫さまが弾く楽器”のような、敷居の高いイメージがあるかもしれませんが、決してそんなことはなく、老若男女を問わずどなたでも気軽に楽しむことのできる楽器です。
もっと見る
〝コト〟というと、「琴」が常用漢字なため、
「琴」と表記するんじゃないの?と思われる方もいらっしゃると思いますが、「箏」の字が使われるようになったのには、歴史に基づいた理由があります。
コトの歴史は古く、静岡の登呂遺跡から発掘されたことから、少なくとも2千年前から日本にあったとされています。
日本古来のコトは、6本の絃が張ってある〝和琴〟と呼ばれるもので、ギターやバイオリンのように、左手の指で絃を抑えて音程をつくり、右手の指で直接絃を弾くのが特徴です。
派生楽器である一絃琴、二絃琴も同様です。
対して、奈良時代に中国から伝わったとされ、13本の絃を有し、柱を立て、右手の指にはめた爪で奏するコトが、〝箏〟です。
琴も箏もどちらも〝コト〟と呼ばれ、やがて、柱がないコトを「琴(きん)のコト」、柱を立てて奏するコトを「箏(そう)のコト」と、区別するようになりました。
ところが、次第に箏のコトが主流となり、琴のコトが演奏される場面が極端に少なくなったことを理由に、箏のコトを一般的な〝コト〟と呼ぶようになり、表記も「箏」の字が使われるようになりました。
江戸時代に、八橋検校により現在の形に改良されるとともに、奏法や楽式も新たに確立され、大きく発展した箏。(京都の銘菓「八ツ橋」の由来となったという説もあります。)
絃の本数が13本の箏を基本とし、時代とともに十七絃、二十絃、二十五絃、三十絃と、絃の本数の多い箏がつくられました。
遡ると、八橋検校を筆頭に、宮城道雄や沢井忠夫といった箏の先駆者により様々な奏法が取り入れられ、西洋音楽の影響も受けてきた歴史もあるため、時代に合わせて色々な意味でバリエーションが増えたのは、必然ともいえるでしょう。

三絃とは
三絃は、三味線の別称です。
〝三味線〟の方が聞き馴染みがあるかと思いますが、
三味線音楽のジャンルの一つである地歌や箏曲では、基本的に〝三絃〟と呼ばれます。
三味線には、太棹・中棹・細棹の3種類がありますが、
地歌や箏曲では中棹を使用します。
古くは地歌の伴奏楽器として広まりましたが、やがて、
箏や尺八に合わせて演奏されることも多くなりました。
箏と同じく、格式が高く年輩の方が演奏するイメージを持たれがちですが、
近年では色々なジャンルの音楽で使用されています。
エンターテイメントとして、和テイストなエッセンスを加えたいときに使われたりなど、
現代では気軽に楽しめる楽器として、年齢や性別、国籍を問わず親しまれています。
もっと見る
三絃はその名の通り、三本の異なる太さの絃を、撥を使って鳴らす楽器です。
絃を弾くのと同時に撥を皮に打ち付けて演奏するため、打楽器としての要素も持ち合わせています。
古くは、中国から原形となる楽器が沖縄に渡り、蛇の皮が貼られた三線として沖縄に定着します。
そして上方(現在の近畿地方)へ渡り、胴の部分に猫や犬の皮を用いた、
太棹・中棹・細棹の三種類がつくられ、
さまざまな三味線音楽が誕生しました。
義太夫節や新内節などの浄瑠璃や津軽では太棹、
地歌や民謡では中棹、長唄では細棹が使用されます。
地歌以外の三味線音楽では、三味線奏者が器楽部分、歌い手が歌唱部分を担当し、
完全分業となっていますが、地歌は弾き歌いで演奏するのが基本です。
三絃とは
三絃は、三味線の別称です。
〝三味線〟の方が聞き馴染みがあるかと思いますが、三味線音楽のジャンルの一つである地歌や箏曲では、基本的に〝三絃〟と呼ばれます。
三味線には、太棹・中棹・細棹の3種類がありますが、地歌や箏曲では中棹を使用します。
古くは地歌の伴奏楽器として広まりましたが、やがて、箏や尺八に合わせて演奏されることも多くなりました。
箏と同じく、格式が高く年輩の方が演奏するイメージを持たれがちですが、近年では色々なジャンルの音楽で使用されています。
エンターテイメントとして、和テイストなエッセンスを加えたいときに使われたりなど、現代では気軽に楽しめる楽器として、年齢や性別、国籍を問わず親しまれています。
もっと見る
三絃はその名の通り、三本の異なる太さの絃を、撥を使って鳴らす楽器です。
絃を弾くのと同時に撥を皮に打ち付けて演奏するため、打楽器としての要素も持ち合わせています。
古くは、中国から原形となる楽器が沖縄に渡り、蛇の皮が貼られた三線として沖縄に定着します。
そして上方(現在の近畿地方)へ渡り、胴の部分に猫や犬の皮を用いた、太棹・中棹・細棹の三種類がつくられ、さまざまな三味線音楽が誕生しました。
義太夫節や新内節などの浄瑠璃や津軽では太棹、
地歌や民謡では中棹、長唄では細棹が使用されます。
地歌以外の三味線音楽では、三味線奏者が器楽部分、歌い手が歌唱部分を担当し、完全分業となっていますが、地歌は弾き歌いで演奏するのが基本です。

地歌とは
〝地歌〟と書いて字のごとく、地声で太くまっすぐ歌い、箏や三絃に合わせた〝弾き歌い〟を特徴とします。
三味線音楽のジャンルの一つで、古くは歌舞伎の伴奏音楽として演奏されていました。
その後、地歌に代わって長唄が歌舞伎で扱われるようになり、地歌は一つの音楽の形態として独立します。
やがて箏曲と結びついたことで、箏や尺八または胡弓に伴う音楽としても大きく発展しました。
子供から始めることができ、男性も女性も同じ音域で歌うため、
合奏の際に男女で一緒に歌ったり、歌い分けることもできます。
もっと見る
地歌は、西洋のオペラなど裏声を使う歌唱とは対照的に、
字の通り〝地声〟を用いる歌唱の三味線音楽として、上方(現在の近畿地方)で発展しました。
元禄時代頃までは、江戸でも歌舞伎の伴奏音楽として演奏されていましたが、
長唄が歌舞伎の伴奏として確立してからは、次第に演奏されなくなりました。
その後単独で発展し、江戸の幕末までには京阪を中心に東は名古屋、西は中国、九州に至る範囲で演奏され、
明治以降は生田流箏曲に付随する形で東京にも再進出し、急速に広まりました。
地歌舞の伴奏音楽のイメージもあるのですが、地歌舞で演奏される曲は伝承されている曲の一部で、
箏曲としては多くの曲が演奏されています。
三味線音楽として誕生した地歌ですが、先述のとおり箏曲に付随して発展したため、箏の独奏でも歌われます。
地歌とは
〝地歌〟と書いて字のごとく、地声で太くまっすぐ歌い、箏や三絃に合わせた〝弾き歌い〟を特徴とします。
三味線音楽のジャンルの一つで、古くは歌舞伎の伴奏音楽として演奏されていました。
その後、地歌に代わって長唄が歌舞伎で扱われるようになり、地歌は一つの音楽の形態として独立します。
やがて箏曲と結びついたことで、箏や尺八または胡弓に伴う音楽としても大きく発展しました。
子供から始めることができ、男性も女性も同じ音域で歌うため、合奏の際に男女で一緒に歌ったり、歌い分けることもできます。
もっと見る
地歌は、西洋のオペラなど裏声を使う歌唱とは対照的に、字の通り〝地声〟を用いる歌唱の三味線音楽として、上方(現在の近畿地方)で発展しました。
元禄時代頃までは、江戸でも歌舞伎の伴奏音楽として演奏されていましたが、長唄が歌舞伎の伴奏として確立してからは、次第に演奏されなくなりました。
その後単独で発展し、江戸の幕末までには京阪を中心に東は名古屋、西は中国、九州に至る範囲で演奏され、明治以降は生田流箏曲に付随する形で東京にも再進出し、急速に広まりました。
地歌舞の伴奏音楽のイメージもあるのですが、地歌舞で演奏される曲は伝承されている曲の一部で、
箏曲としては多くの曲が演奏されています。
三味線音楽として誕生した地歌ですが、先述のとおり箏曲に付随して発展したため、箏の独奏でも歌われます。


年齢や性別を問わず、どなたでも気軽に始められます。
無料体験や楽器レンタルもあるので、初めてでも安心です。
古典曲からポップスまで幅広く習得でき、和の音色でストレス解消も期待できます。
【伝統文化で豊かな心を育む】
- せっかく日本人として生まれたし、和に関する習い事を始めたい
- 以前やっていた箏や三絃をまた習いたい
- 〝大和なでしこ〟というワードが似合う女性になりたい
- 品のある女性として、素敵な歳の取り方をしたい
- お子さんに、日本の伝統に触れる経験をさせてあげたい
また、
- コンクールに挑戦したい
- 音高・音大を受験したい
- プロの演奏家になりたい
こんな方は、お気軽にお問い合わせください。

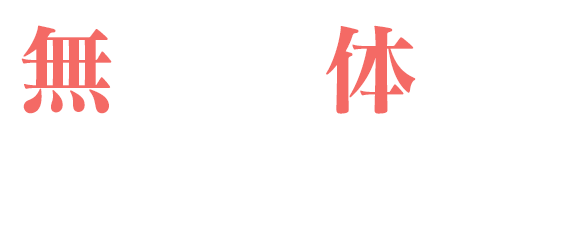
箏や三絃を弾くことが初めての方もご経験のある方も、まずは無料で体験していただけます。
一人が心細い方でも、お友達やご家族と一緒に体験していただけるので、どうぞ気軽にお問合せください。



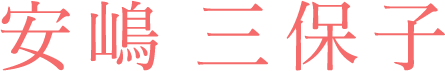
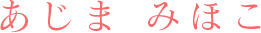
生田流箏曲(箏・三絃)演奏家。東京藝術大学邦楽科卒業、大学院修了。「伝統芸能プロジェクトチーム TRAD JAPAN」に所属。「賢順記念くるめ箏曲祭全国箏曲コンクール」はじめ、数々のコンクールで受賞歴を持つ。
現在は講師業を行いながら、NHK Eテレ「ムジカ・ピッコリーノ」、NHK FM 「邦楽百番」 などメディアへの出演、「サントリー“ROKU GIN”」のCM音楽や「藤間勘十郎 春秋座 名流舞踊公演」の舞台音楽の作曲、歌舞伎「風の谷のナウシカ」の劇中音楽の録音に参加するなど、作曲家・奏者としても活動中。